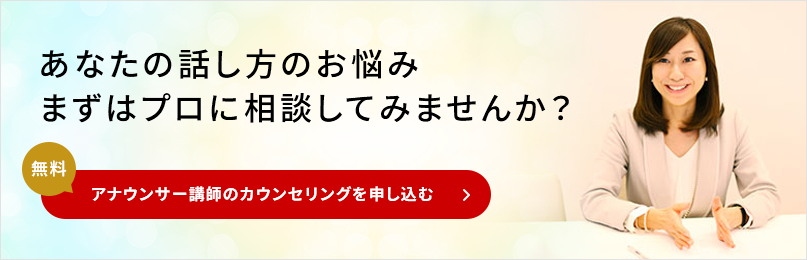「プレゼンの準備をしてきたのに、いざ本番になるとうまく話せない」「相手の反応が薄く、伝わっているか不安になる」「内容をまとめきれず、結局長くなってしまう」
――こんな悩みを抱えたことはありませんか?
実は、プレゼンの成否は「伝え方+資料」が大きく影響します。内容だけを重視している方は要注意です。どれだけ良いアイデアを持っていても、自分の伝えたいことが正しく相手に届かなければ成果にはつながりません。
今回は、話し方のポイントと資料作成の基本を含めたプレゼン成功のための5つのコツをご紹介します。
コツ①プレゼンの第一声はトーンが勝負
プレゼンは第一声で印象が決まる、といっても過言ではありません。冒頭の声のトーン次第で「このプレゼンを聞きたい」と思わせられるかどうか決まります。さらに、ボリュームのある声を出すことは聞き手にインパクトを与えることにつながります。あなたの声のスケール感と明るさが成功への第一歩なのです。
腹式呼吸で安定した声量を出す
明るいトーンは裏返りそうで不安だという方もいらっしゃいます。でも、安定した声量があれば堂々と話している印象を与えることができるのです。声のボリュームを出すために練習したいのは、「腹式呼吸」です。腹式呼吸はその名の通り、お腹を使って息をたっぷり吸い込み、吐き出します。お腹を使った呼吸法に慣れたところで、息を吐くときに声を出してみてください。普段よりも伸びやかな声が出ることを実感できるでしょう。お腹を意識した発声方法は、緊張で声が震えやすい人にも効果的です。「腹式呼吸」を習得して、会場の後ろまでしっかり届く安定した声量を手に入れましょう。
「ソ」のトーンで快活な印象に
プレゼンの第一声で意識していただきたいのは、「ソ」の高さの声を出すことです。普段の会話の音階(ド)より少し高い「ソ」のトーンで話すと、明るく快活な印象を与えられます。
試しに「こんにちは。○○です。」と一言「ソ」のトーンで話してみてください。自信を持って話している印象に聞こえませんか。さらに、「ソ」の音を出そうとすると、表情も自然と明るくなります。プレゼン中、終始生き生きと話している印象を聞き手に与えられるでしょう。特に冒頭のあいさつや自己紹介で実践していただくと、聞き手の関心を引きやすくなります。
キレのある発音でメリハリを
ボリュームのある、明るいトーンに加え、1音1音が明瞭に発音できていれば、プレゼンの第一声は成功です。発音が曖昧だと、どんなに良い内容でも伝わり方が弱くなります。音の特徴を意識して「キレのある発音」を心がけましょう。
例えば、下記が気を付けるべき点です。
•カ行:奥歯を強く噛むようにして発音する
•サ行:上の歯と下の歯の隙間から息を出すように発音する
発音の正しいやり方を意識するだけで、言葉にメリハリが生まれます。音がクリアになることで、聞き手の理解が進み「デキる人」の印象を与えることができます。
声は生まれつきでも、伝わり方は「技術」で変えられます。発声やトーン、発音はトレーニングで確実にスキルアップします。聞き手に伝わる第一声を意識することで、あなたの声は「聞き手を惹きつける武器」へと進化していきます。
コツ② プレゼン資料作成の法則「シンプル&一目で伝わる」
プレゼンでは、「資料のわかりやすさ」が内容と同じくらい重要です。情報を詰め込みすぎた複雑なスライドでは、このプレゼンは何を伝えたいのかが分かりません。聞き手に「結局何を伝えたいの?」と負荷を与えてしまいます。聞き手にストレスを与えることは、プレゼンに集中できない要因にもなります。資料は「一目で要点が伝わる」ことを意識して設計しましょう。
結論を冒頭で示す
スライドの最初には、必ずそのページの結論を端的に配置します。
「結論 → 理由 → 補足」という順序を守ると、聞き手は短時間で理解しやすくなります。
1スライド1メッセージを徹底する
情報を詰め込みすぎず、1枚に込めるメッセージは1つに絞りましょう。
「1スライド=1メッセージ」を守ることで、聞き手は迷わず内容を受け取れます。補足要素は最大3点までが理想です。
聞き手を巻き込む問いかけを入れる
資料は一方的に説明するための道具ではありません。
「この方法とあの方法、成果が出たのはどちらだと思いますか?」といった問いを織り交ぜることで、聞き手の思考を促し、集中力を高めることができます。
資料作成の鉄則は「シンプル」「一目で伝わる」「聞き手が能動的に理解できる」こと。
結論の提示、メッセージの絞り込み、問いかけの工夫を意識すれば、プレゼン全体の説得力が大きく高まります。
コツ③ 冒頭5秒で聞き手を掴む
プレゼンの成否は、冒頭のわずか5秒で決まると言っても過言ではありません。聞き手の心を一気に引き込むためには、「つかみ」の工夫が欠かせません。ここでは、シンプルで実践しやすい3つのパターン「は・ほ・ふ」をご紹介します。
「は」のつかみ ― 驚きを与える
聞き手を「ハッ」とさせるつかみです。
数字やデータを提示すると効果的。
例:「実はビジネスパーソンの70%がプレゼンに苦手意識を持っています」
「ほ」のつかみ ― 和ませる
聞き手の心を「ほっ」と和ませるつかみです。
共感やちょっとした笑いを誘う表現が効果的。
例:「この場に立つと、皆さんからの熱いまなざしで心臓がバクバクして破裂しそうです」
「ふ」のつかみ ― 考えさせる
聞き手が「ふと」考えさせられるつかみです。
問いかけやクイズを交えると、自然に集中を引き出せます。
例:「経営におけるアイデア力を試すクイズを出します」
鉄則は短く5秒以内で伝えること。
堂々とした態度で、ゆっくりと、力強い声を意識してください。場面や聞き手に合わせて「は・ほ・ふ」を使い分けることで、プレゼンの序盤から聞き手を自然に引き込み、成功率をぐんと高めることができます。
コツ④ 緊張を味方にする
「緊張してうまく話せない」と悩む方は多いですが、実は緊張は悪いことではありません。むしろ集中力を高め、パフォーマンスを向上させるサインです。アスリートも「最高の結果を出すためには適度な緊張が欠かせない」と語るほどです。大切なのは、緊張を避けることではなく、コントロールして味方につけることです。
プレゼン環境をイメージして練習する
実際にプレゼンする環境を想像しながら練習すると、本番での「想定外」が減ります。会場の広さや相手の表情をイメージすることで、緊張が徐々に慣れに変わり、落ち着いて話せるようになります。
深呼吸+3秒アイコンタクト
話し始める直前は、まず深呼吸。そして会場全体を見渡すように、3秒間アイコンタクトを取りましょう。これだけで自分の緊張が和らぐだけでなく、聞き手にも「落ち着いている人」という印象を与えられます。
緊張感をエネルギーに変える
「緊張している=真剣に取り組んでいる証拠」と考えるだけで、気持ちは前向きになります。そのエネルギーを声の張りや表情にのせることで、プレゼン全体に説得力が増し、聞き手を引き込む力となります。
そして最後に伝えたいのは――
緊張は“敵”ではなく、最大の“味方”です。
そう思えるようになった瞬間、あなたのプレゼンは大きく変わります。
コツ⑤ プレゼンパフォーマンスで惹きつける
プレゼンでは、高いパフォーマンスを発揮し続けることも求められます。最後の決め手は、話し方そのものに加えて「見せ方」です。プレゼンは1対多のコミュニケーションだからこそ、目線や動作を工夫することで会場全体との一体感を生み出せます。
目線は「1センテンス・1ブロック」
一人をじっと見つめ続けるのではなく、会場を3〜4ブロックに分けて、1センテンスごとに目線を移動させましょう。自然に全体とつながり、「自分に話してくれている」という感覚を持ってもらえます。
ジェスチャーで「数・大きさ・形」を表現
「3つのポイントがあります」と指で示す、「大きな成果」と両手を広げるなど、具体的な動きを取り入れることで説得力が増します。手の動きは言葉を補強する強力なツールです。
「間」を効果的に使う
強調したい言葉の前後で一拍置くと、聞き手の意識をグッと引き寄せられます。また、話題を切り替えるときにも「間」を入れると、理解が深まり、内容が整理されて伝わります。
表情・姿勢・声の抑揚を組み合わせる
プレゼンは「全身で伝える」意識が大切です。笑顔や前傾姿勢、声の強弱や抑揚を組み合わせることで、聞き手は自然と惹き込まれていきます。
最後の決め手は、話し方に加えて「見せ方」です。プレゼンは1対多のコミュニケーションだからこそ、視線や動作を工夫することで一体感を生み出せます。
まとめ
今回ご紹介したプレゼン成功の5つのコツを振り返りましょう。
1. 声とトーンを整えて第一印象を掴む
2. 資料作成は「シンプル&一目で伝わる」が鉄則
3. 冒頭の5秒で「つかみ」を決める
4. 緊張を味方にする
5. プレゼンパフォーマンスで惹きつける
プレゼンを成功させる秘訣は、声・資料・つかみ・緊張対策・パフォーマンスをトータルで磨くことにあります。しかし、これらを自分一人で客観的に改善するのは難しく、自己流ではなかなか成果につながりません。
KEE’S話し方教室では、現役アナウンサーが直接指導し、実際の資料や本番を想定したトレーニングを通じて「聞き手に伝わる力」を伸ばすことができます。
声の出し方からプレゼンの構成、見せ方まで一貫して学べるのが最大の強みです。
まずは無料体験で、“伝わるプレゼン”を体感してみませんか?
 KEE'S 人気アナウンサーの6時間で変わる話し方教室・話し方講座(東京駅・恵比寿駅 徒歩1分)
KEE'S 人気アナウンサーの6時間で変わる話し方教室・話し方講座(東京駅・恵比寿駅 徒歩1分)